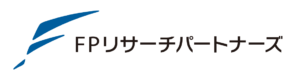確定拠出年金
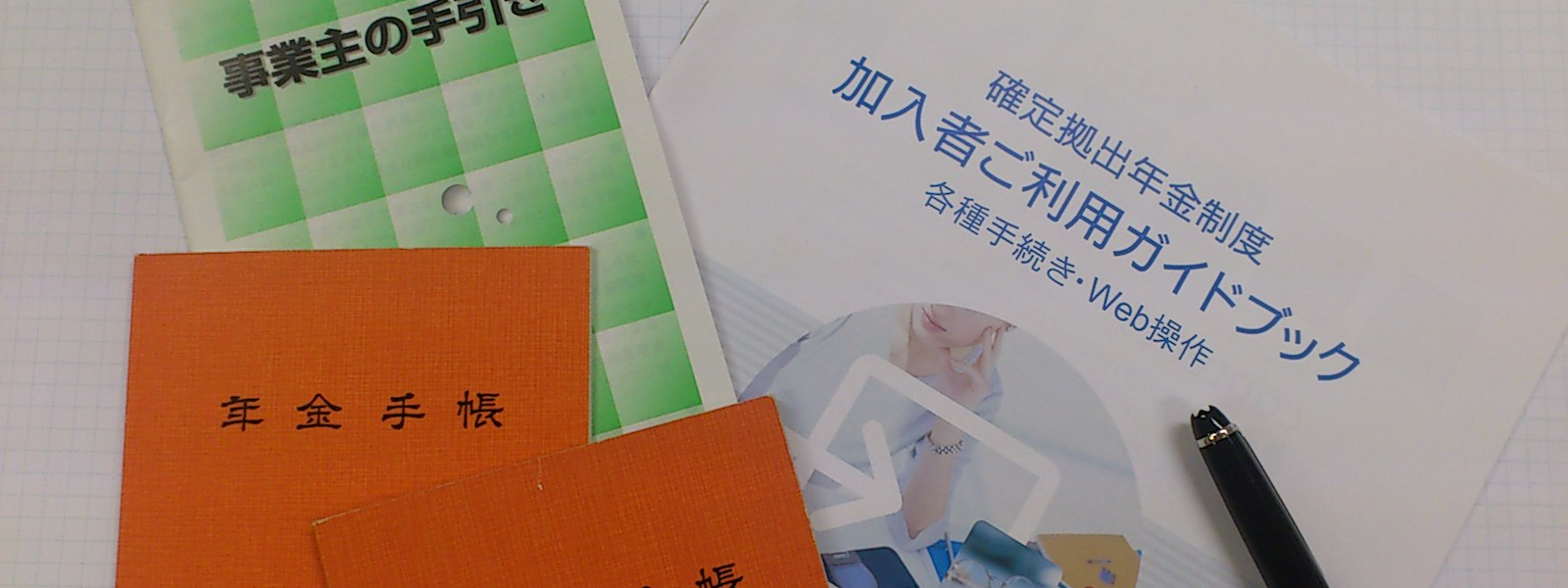
老後資金準備が有利な確定拠出年金(401k)とは?
確定拠出年金は「公的年金」の上乗せ年金の位置付けで今後も普及が進む制度です。企業が退職金制度として加入しているケースもありますし、個人が独自で加入(iDeCo)するケースもあります。普及が進む背景としては少子高齢化の加速により将来的に年金支給年齢を引き上げたい思惑があります。既に諸外国が年金支給開始年齢を引き上げている今、65歳から今後も受給できるとは限りません。
年金制度を維持するためには「年金受給開始年齢の引き上げ」「年金額の減少」が必要とされます。公的年金だけでは不足する分を確定拠出年金を使い節税しながら老後資金を確保しましょうという国からのメッセージも込められていると感じています。
年金の不足分を用意する一般的な方法として、「個人年金」「投資信託の積立投資」「預金」、場合によっては「不動産投資」など様々な方法が使われていますが他の方法と比較してのメリットを知りましょう。まずは確定拠出年金制度を使う方法が良いでしょう。
■最大のメリットは所得控除
- 掛け金が全額所得控除
- 運用益が非課税
- 受け取り時は公的年金の所得控除
- 個人別に分別管理
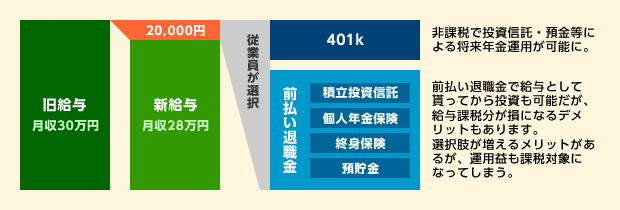
ずっとNISA効果かつ節税
最大のメリットは確定拠出年金で積立てる掛け金は「所得控除」できるということです。毎月2万円を積立た場合は年間24万円の所得控除になります。所得税・住民税で20%課税されている場合は4.8万円の節税効果があります。24万円で年4.8万の間接的利益があるため定期預金で運用すれば「年利20%」の投資をしているようなイメージです。所得税率が高い方は一層効果が高まります。また利益に対しても非課税のためNISAをずっと使えるようなイメージでメリットは「節税」です。
■デメリットは「60歳以降」の受け取り
メリットが目立つ確定拠出年金も大きなデメリットが大きく2つあります。ひとつは積立てた年金資産は60歳以降でないと引き出すことが出来ません。そのため急に資金が必要となった場合などを想定しておかなければなりません。個人年金や終身保険などで積立している場合、途中解約で減額されてしまいますが、途中で引き出すことができます。そのため毎月の掛け金は無理のない程度にしておく必要があります。節税効果が高いため、限度値まで掛金を増やすケースがありますが、途中で積立額を変更することができます。
また多少のランニングコスト(口座管理等)が掛かりますがネット証券などが提供しているiDeCoの場合コストは比較的低くなっています。商品数やコスト等を考慮するとSBI証券のiDeCoを推奨しております。以下の案内から申込いただけます。
SBI証券のiDeCoの案内へ ※別画面で開きます。
■掛け金の投資運用
毎月の掛け金は「自分で選択」する必要があります。投資に興味がある方にはメリットかも知れませんが、投資に不安がある方にはデメリットになってしまいます。ただ投資配分は複数の商品を選択できるため、「定期預金50%、日本株式20%、外国債券30%」など分散投資をすることが可能です。
また基本的にはインデックス投資商品(相場に連動するもの)と元本保証商品から選択しますのでしっかりと自分のリスクに応じた分散投資が出来れば将来の年金を増やすことも可能です。
確定拠出年金の投資運用で必要な心得は如何にして「50歳~60歳付近で資産を最大」にするかがポイントになります。
リスクなしの場合は定期預金
運用商品には必ず元本保証型の商品のラインナップがあります。節税はしたいけれど、運用のリスクは・・・とお考えの方は定期預金などを選択することで投資リスクをなくすことが出来ます。
■ご相談料金
| 確定拠出年金コンサルティング | 確定拠出年金の投資運用や自分にとっての効果などを具体的にご説明します。また他の方法と比較を行ったりすることが可能です。加入する前に制度をしっかりと理解したい方や会社で制度が導入された方などをサポートしております。
6,600円(税込)本体価格:6,000円 |
|---|